取材趣旨:企業インタビュー
1969年に産声を上げた協同工芸社は、看板の企画から、製作・施工・アフターメンテナンスまで一貫した体制で顧客と向き合い、その50年近い歴史を、生粋の「看板屋」として刻み続けてきた。創業者から箕輪社長へとバトンが渡されたのは2014年。箕輪社長は中途として25歳の時に同社へ入社。一社員として入社した箕輪社長は、めきめきとその頭角を現し、専務の役職を経て同社の代表取締役社長に就任。その箕輪社長が就任して初めて取り組んだ施策は「人を採ること」。施策は成功し2016年には「はばたく中小企業・小規模事業者300社」において人材部門で選出されたほどだ。本取材では箕輪社長の人に対する思いや施策、また「看板屋」としての今後の展望に迫った。
伝統の継承と、
目次
伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質
社員の豊かな想像力を生かす自由さ
社員が自由に動き、考えることを尊重している箕輪社長。近年、社内を活性化すべく始まった「委員会活動」は、まさに社員が自主的に動いたことによる企画だ。ここ2・3年の間に、何もなかった状態から8つの委員会が開かれるようになり、新製品開発委員会・品質向上委員会等、今や、あらゆる角度から会社を活性化する「委員会活動」が存在する。様々な部署から自主的に集まったメンバーで毎月1回集まって、改善提案を考え社内に掲示する、この一連の流れを箕輪社長が一切関与することなく、全て社員だけで行っているというから驚きだ。「(社員たちが自発的に動く)仕組みになっているのでしょうね。新製品を考える委員会もあるので、そこからこういうものをつくりたいですと自発的に声があがることを期待しています」と、箕輪社長は語った。「ものつくりをしたい」「デザインをしたい」という思いで入社した社員が多く、その豊かな創造力を生かすことのできる環境が同社にはある。
よそでは作れない技術を
「よそでは作れない技術を作る」。箕輪社長はこれを強く意識している。多くの企業が商品の販売促進にのみ傾倒する中、企業は販売促進・組織作り・商品開発が三位一体となって発展していくべきだと箕輪社長は考える。そして中でも重きを置いているのが商品開発だ。「当社はおよそ50年の歴史を持つ『看板屋』です。看板について積み上げられた実績とノウハウ、これこそが当社の優位性であり、今後も磨くべきポイントだと考えております」そう語る箕輪社長。現在では看板の企画から施工までワンストップでサービスを提供できる同社。だからこそ技術が進化すればするほど同社の仕事の幅は大きく広がる。同社は看板を通じてお客様の思いを実現する会社だと銘打っており、看板づくりの技術を磨いてきたからこそ、現在に至るまでに関わったお客様から高い評価と満足度を得ている。上述の箕輪社長の思いのもと、今後更なる発展を遂げた同社は間違いなく随一の「看板屋」となっているであろう。
女性がより一層に活躍できる企業へ
協同工芸社が目指すのは、「女性が活躍できる会社」のモデル企業となるという将来だ。近い将来に人口減少が加速していくことが問題視されている中、就労人口の減少は多くの企業にとって大きな痛手となる。そういった時代の波に飲みこまれていくことなく発展を続けるために同社は、女性がより一層に活躍できる企業を目指す。女性は出産、育児など人生の節目で仕事を同じペースで続けることが難しい状況となることも往々にしてある。しかし、そういった状況は永遠に続くわけではない。実際に同社では出産、育児を終えた女性が同社に戻ってきたいという要望を受けて女性が職場復帰できるようなシステムが構築されつつある。例えば、9時に出社して3時に退社するような時間短縮社員の枠をもうけたり、在宅勤務も可能なように就業規則を変更している。これによって実際に職場復帰する女性社員が同社に既に出てきている。こうして時代の波を捉え、同社は発展を続けていくのだ。
箕輪社長の社員にかける思いに迫る
新卒の社員が増えてきている中若手社員にどういった取り組みをされていますか
色んなことをチャレンジさせるようにはしています。自分たちの能力を外に出て挑戦して、発揮する機会を与えることは、会社として行っていくべきことだと思うのです。もとより、成果次第では、社内としては1年目、2年目から活躍できる会社でもありますが、それだけではなく、社外のコンテストに1年目だけで応募させるといったようなチャレンジの機会を与えることもあります。困難なことを乗り越える力は大切ですよね。こうした機会を通じてそういった力を身につけてもらって、会社の屋台骨を支える人間に育って欲しいです。これからも、社員が成長の機会に積極的にチャレンジできるシステムを作っていきたいと考えております。
若手社員への取り組みによってどう育ってほしいとお考えでしょうか
一人一人が「ミニ経営者」となってほしいと考えています。経営というもの丸い円のようなもので、その円を全部自分で把握する必要はない。むしろ、経営という円の一部を得意な人がサポートして、経営を回している状態の方が良いのです。今はその為に、自身の得意な部分を生かして経営のサポートを出来る人を育てています。弊社は「ものをつくりたい」、「デザインをしたい」という思いで入社した社員が多い会社ですが、目の前の仕事に取り組むのみならず、どこに手を打てば利益が上がるか、などを考えるようになってもらったりと、経営にも目を向けながら働く方こともまた面白いのではないでしょうか。
今後の事業に関する方針を教えてください
弊社は、ものつくりの好きな人たちが集まる会社です。広告代理店ではなく、ものつくりの会社として発展していきたいと考えております。お客様対応などのソフト面ももちろん大事ではありますが、ものつくりのハード面の強い会社でありたい。そうすることでお客様の多様な要望に応え続け、世に求められる企業になっていきたいですね。ある意味、時代に逆行しているのかもしれません。だからこそ「看板屋」として専門性を強化したいと思っています。弊社においては「現場に力を」という基本方針を持っておりますので、設備の充実、技術力の強化に力を入れることを優先していきたいと思っています。

企画部は特に女性が多く働いています

社員の作業を確認します

社長自ら作成する社内報
協同工芸社のこれからを担う期待の星
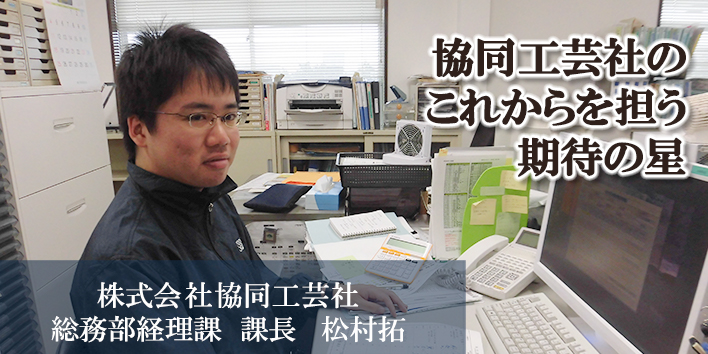
株式会社協同工芸社 総務部経理課 課長 松村 拓
協同工芸社は製造業としては珍しく、近年若い人材が急増している会社だ。世の中の製造業の社員平均年齢がおよそ44歳である中、現在、同社社員の平均年齢はなんと31.7歳。今回取材させていただいたのは新卒採用を始めて4年が経つ同社で、新卒2期生として入社し現在入社3年目となる松村さん。松村さんは、入社してすぐに営業部に配属となり、その営業の実績を買われて、1年目に営業主任、2年目には課長に昇格した若きエースだ。今回の取材では、松村さんが入社を決意した理由から、「看板屋」ならではのエピソード、先日、営業から総務へと異動した理由でもある、松村さんが思い描く夢まで、お伺いした。
伝統の承継と挑戦の未来を担う社員の思い
中小企業で経営に携わりたい
松村さんが同社に入社する決め手となったのは、協同工芸社ならば経営に早くから携わることが出来るという確信を持てたこと。大学時代に得た経営学の知識を生かしたいと考えていた松村さんは早くから経営に携われる企業に就職したいと考ていた。地元である、千葉県の企業限定の合同説明会で、当時専務であった箕輪現社長に声を掛けられたことをきっかけとして同社を知り、魅力を感じ、営業として入社することを決意。複数ある同社の部署の中で営業を選んだ理由として松村さんは「人と話すことがあまり得意じゃないので、一回やってみたいと思いました」と話した。コミュニケーションに対する苦手意識に正面から向き合い、挑んできた松村さん。苦手意識もなんのそので1年で主任へと昇格。2年目の10月には同部署の課長にまで昇格した。そこで培った営業の知識を生かし、3年目の11月半ばに総務部経理課に異動になった現在、営業の経験を持つ総務として社内から会社を支えたいと考えているという。
各地に残る仕事の想い出
「自分が携わった仕事がずっとその街に残るというのは、いいものですよね」と松村さんは笑顔で語る。「思い」を伝える看板づくりの為、1つ1つ丁寧な工程で施工まで行った看板は、一度取り付けたら、何年もの間、店の顔となり、その街に残り、店の正面を飾り続けるものとなる。ふらっと訪れた場所に、自分が手掛けた看板があることに気付いた時に、この仕事を続けてきてよかったと感じたという松村さん。協同工芸社の看板が設置されている場所も多様で、松村さんが携わった全国各地の有名な飲食店からテーマパークといったように、日本全国を飛び回っていたそう。その為、忙しなく移動する時もあり、たった1日で四国から秋田へと営業に回ったことや、日帰りで沖縄に打ち合わせに行ったこともあるのだという。「自分が携わった看板が、今ここにいるときも沖縄にあると思うと、この仕事を続けていてよかったと思います」と語った。まさに「看板屋」ならではのやりがいを松村さんは感じ、日々の仕事に向き合ってきたのである。
新入社員が勧めたくなる企業づくりを支えたい
松村さんの夢は、「新卒で入った社員が入社を勧めたくなるような会社にする」こと。一般的に良い会社に入社しても、本人が満足するが、なかなか紹介しようと考える人は少ないのではないだろうか。その中で松村さんは協同工芸社を思わず後輩に入社を勧めたくなるような会社にしたいと思い描いているのである。総務に異動になる前に、営業として社外との関係、その最前線を知ったことで、社員がより働きやすくなるために考え、元営業の総務として会社に貢献できないかと考えている。「表の人(社外と取引する営業等)のことを知らない状態で、何か変えようとすることはできないじゃないですか。知っているからこそ、裏側に回って考えた改善案を表の人に信用してもらえる」と話す松村さん。これからは総務という立場で社内を見つめ、裏も表も知っている総務として、社員がつい紹介したくなってしまうような会社を目指し、よりよい職場環境作りを取り組んでいくに違いない。

新入社員だけでチャレンジしたオブジェ

工場内での打ち合わせの様子

黙々と仕事に打ち込む職人
営業として感じていた、仕事に掛ける想いを伺った
教育はどのように行っているのですか
今回の総務への異動前まで、営業として新人教育を行っていた時は、現場に行って教える、そして見て覚えるという形を取っていました。新人は、1年~2年位で1人前になることはできますが、そこは人によりけりですね。基本的に営業は個人技な部分も大きいので、新人も最初は先輩に同行してもらって現場に行きますが、早い段階で、1人で現場に出ていくことになります。現場に出るタイミング以外で、営業を行っていく上で、工場にて、ものに関する知識を覚える必要などもありますし、現場では見て覚えるところが大きいので、営業に限らず、熟練の技術を継承していく為にも、これからより一層しっかりと教えられる教育体制を構築していければと考えています。
会社の好きなところを教えてください
3年目でこれだけのことを任せてもらえるのかと思うほどに仕事を任せていただき、色々と経験をさせていただいております。実績や日頃の仕事の姿勢から、この人ならできるなと思っていただければ年数には左右されず、仕事を任せていただけます。少数精鋭ということもあって、個人に与えられる裁量も大きいので、やりがいがあります。それこそ、経営に携わりたいという希望も通り、社外を見ている営業から社内を見ている総務へと異動したことで、総務の業務と共に、3年目にして経営の中枢を見させていただけるので、こういったことは、他に類を見ない協同工芸社だからこそできていることではないかと思っております。
嬉しかったエピソードを教えてください
お客様の嬉しい驚きの声を聞いた時ですかね。看板を設置する3か月前に、一度何もない状態で見に行くのですが、その2か月後に再度訪れてみると現場の様相が一変します。看板は最後に付けるので、建造、内装、設備など、あらゆる工程が全て終わった際に、最初想定していたものと全く異なっていることもあります。実際に看板は付けてみないと分からないのです。もちろん、事前にお客様と紙の上で図面として見て打ち合わせしますが、紙の上に書くだけではわからないことが多くあります。打ち合わせを行い、状態に合わせて作り直したりと試行錯誤を繰り返した看板が完成した時、お客様から、「思ったよりいいね」と言われた時はやっぱり嬉しいですね。次も頑張ろうと思えます。
担当者からのコメント

-
監修企業 担当者
協同工芸社は将来的な「人材の多様化」に向けて、様々な施策を打ち、今勢いのある企業。社内では多くの女性が生き生きと働かれている姿が見られ、箕輪社長の話された「女性活躍」の一端を垣間見ることが出来ました。私たちの日常の中に溶け込んでいる看板も、生き生きと働く協同工芸社の社員の方々によって創られたものだと思うと、また、日常的に見ていた景色も違って見えてきました。これから更に、協同工芸社の手掛ける看板を目にする機会が増えていくこととなるでしょう。
掲載企業からのコメント

-
株式会社協同工芸社 からのコメント
弊社のように、オートメーションによる機械的制御ではなく、基本的に人によって動かしている企業にとって、これから先「人材の多様化」していくことは不可欠です。「看板屋」であり、「ものつくり」が好きな会社として、拡大を続けていきたいと思います。
企業情報
-
創業年(設立年)
1969年
-
事業内容
屋外広告・大型ネオン看板等の企画提案/設計・デザイン/看板製作・施工/各種申請業務/店舗内装工事/ 保守・管理&メンテナンス
-
所在地
千葉県千葉市美浜区新港152
-
資本金
1000万円
-
従業員数
93名
- 会社URL
沿革
-
1969年~1995
1969年 2月
設立
1969年 7月
本社工場を建設
1970年 11月
弘報社印刷広報部を合併
1975年 9月
新工場建設
1977年 7月
本社事務所を増設
資本金300万円に増資
1988年 9月
本社ビル建設(新第一工場建設)
1990年 7月
蘇我第三工場設置
1994年 9月
新第二工場建設
1995年 7月
資本金1000万円に増資 -
2003年~2015年
2003年 6月
建築設計事務所登録
2005年 10月
隣接地購入(幕張第三工場)
蘇我第三工場を幕張第三工場に移転
2014年 5月
代表取締役に箕輪晃就任
東京支店を開設
経営革新計画に係る承認認定
2014年 10月
関東経済産業局の「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づき
特定研究開発等計画について認定
2015年 3月
千葉県優秀企業経営者表彰にて「知事賞」に選出
2015年 10月
千葉市美浜区新港152に本社移転
取材趣旨:企業インタビュー
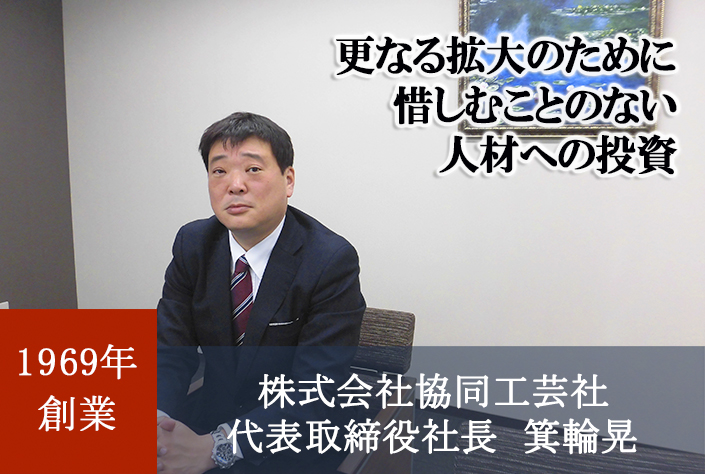





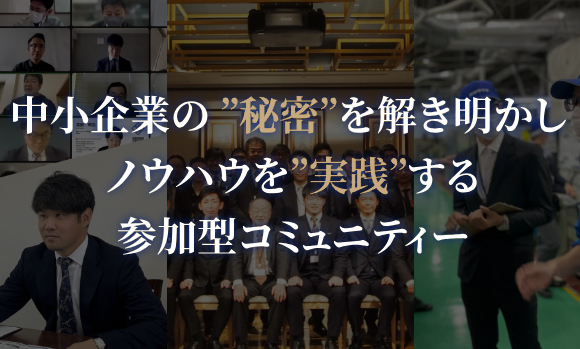
 ">
"> ">
"> ">
">


